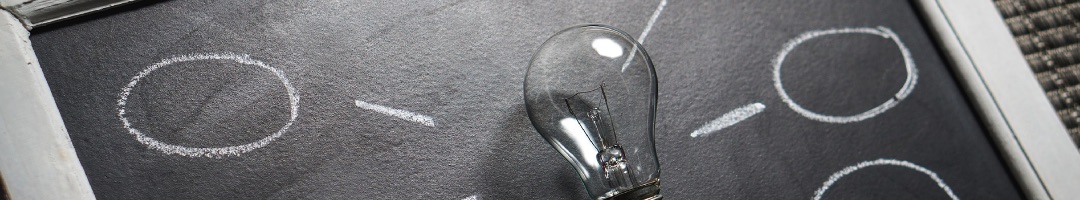小線源治療部会第26回学術大会の見どころ:安藤 謙先生
こんにちは。最終回は小線源治療部会第26回学術大会の見どころについてご紹介します。
改めてご紹介しますと、小線源治療部会第26回学術大会は2024年5月25日(金)、 26日(土)に当教室の大野達也教授を大会長として高崎のGメッセ群馬で開催されます。小線源治療部会は毎年1回開催される、放射線治療の中でも小線源治療に焦点を当てた学会です。小線源治療部会と当教室との縁は深く、当教室出身の先生では 2007年中野隆史先生、2015年加藤眞吾先生、2017年長谷川正俊先生、2018年櫻井英幸先生が大会長を歴任されています。
今回の小線源治療部会では「つなぐ、つながる小線源治療の未来」をメインテーマとして、小線源治療を取り巻くさまざまな「つながり」について、その現状と課題、未来へ の展望を議論します。学会プログラムは http://gc-support.jp/2024jgb/03_program.php をご参照ください。以下に注目するプログラムをそれぞれの「つながり」を ポイント毎にご紹介します。
1.技術革新のつながり 小線源治療は、先人達の英知に新たな技術革新を取り入れて発展してきました。以下のセッションではエキスパートの先生方のノウハウと未来への展望を聞くことができ ると期待しています。
・第1日目 第1会場 10:10〜 シンポジウム1「小線源治療とイノベーションの継承」
・第1日目 第2会場 14:40~ 要望演題1 「症例からの教訓:なぜやる?なぜやらない?」
・第2日目 第1会場 13:30~ シンポジウム3 「AIで小線源治療はどこまで進化するか」
・第2日目 第1会場 15:10~ 要望演題3 「小線源治療のArtとSkill」
2.医療安全に向けたつながり 小線源治療も外部照射に追従して高度化が進んでおり、高度医療の提供は 医療の質の担保と患者安全とが両輪をなすことが求められます。従来の多職種からなる チーム医療の取り組みに加え、最近では患者参加型医療も注目されており、以下の セッションではその取り組みが聞けると思います。
・第2日目 第1会場 9:40~ 特別講演2 「患者安全の全体像と展望」
・第2日目 第1会場 10:40~ ワークショップ1 「安全・安心な小線源治療のために」
3.地域連携のつながり 放射線治療が行える可能な施設の中でも、小線源治療が可能な施設は限られるため、地域の医療機関や他診療科との連携に基づく集約化・効率化が求められています。
・第2日目 第2会場 13:30~ 要望演題2 「小線源治療を支えるネットワーク・コミュニティ」
各地域での地域連携について具体的な取り組みについて議論します。
私もここ数年取り組んでいます群馬県内の多施設連携について発表させていただき ます。
4.世界とのつながり 当教室では、以前よりアジアを中心として近隣諸国の小線源治療の啓蒙・教育に力 を注いでおり、本学会ではその現状を紹介し、今後我々が果たすべき役割について議論します。
・第1日目 第1会場 14:40~ 教育講演2 「日本が果たす小線源治療の国際貢献」
・第1日目 第1会場 16:50~ シンポジウム2 「世界とつながるBrachytherapy: Look Asia! 」
5.手技のつながり 小線源治療は放射線治療の中では数少ない、手技を伴う治療です。当教室が 開発したハイブリッド腔内照射ついて、 実際に手を動かしながら手技を学ぶハンズオンセミナーも第1日目の13:00~開催し ます。当日の参加者はすでに募集を締め切っていますが、希望者は見学可能です のでご連絡ください。
以上、駆け足にはなりましたが今回の小線源治療部会の見どころについてご紹介し ましたが、ここには書ききれない興味深い発表がたくさんあります。短い時間でも構い ませんので、ぜひ会場に足をお運びいただき、熱のこもった発表・議論を体感してい ただければ幸いです。
学生・研修医の先生方で当学会に興味を持たれた方は 是非お気軽にご連絡ください!お越しの際は教室員がアテンドいたします。読者の方のお一人でも多いご参加を願っております。